【説明しない勇気】「以前のやり方」が通用しない理由。医師に選ばれるMR・MSLへの転換点
変化に取り残されたMRにならないために
「以前は先生と雑談できるくらい信頼関係があったのに、最近は何を話しても響かない」
これは、あるベテランMRがこぼした言葉です。私自身の製薬業界での長い経験の中で、こうした声を何度も耳にするようになりました。
従来は、製品知識と誠実な態度があれば、医師との信頼関係は築けるものでした。しかし、プロモ―ション規制の強化、訪問規制の常態化、そして情報提供チャネルの多様化により、「以前と同じやり方」では通用しなくなっています。
特に重要なのは、「説明して伝える」スキルだけでは、もはや医師の心を動かせないという現実です。
これからの製薬パーソンに求められるのは“対話力”
変化するMR・MSLの役割
近年、製薬業界は構造的な変革の波に直面しています。
規制環境の強化(販売情報提供ガイドライン、公正競争規約、臨床研究法など)、パンデミックによる面会制限、さらには「MR不要論」の拡大などにより、従来の情報提供モデルが限界を迎えつつあります。
こうした状況に対応する形で、企業は専門MRの配置やMSLの増員、デジタルツールの導入を加速していますが、それだけでは不十分です。
今、真に問われているのは「医師との信頼関係を築けるか」「相手の課題に迫れるか」という本質的な対話スキルです。
単なる説明は“逆効果”になる
多くのMR・MSLが誤解しているのは、「論理的に説明すれば、医師は納得してくれるはずだ」という思い込みです。
しかし、実際の医師の現場は忙殺されています。
患者対応、治験や自身の研究課題への取り組み、学会発表、組織マネジメントや経営課題など、時間的・精神的余裕が限られる中で、「一方的な説明」は“負担”に感じられることすらあります。
重要なのは、「なぜこの話を今この医師にするのか」という明確な意図と、医師自身がその話題に関心を持てる“導入の設計”です。
ここで鍵になるのが「質問型」の対話アプローチです。
SPIN話法に学ぶ、質問から始まる交渉
SPIN話法は、セールスや交渉において極めて有効なフレームワークで、以下の4ステップで構成されます。
- S(Situation)状況質問:「先生のご施設では、〇〇治療に関してはどのような体制ですか?」
- P(Problem)問題質問:「その中で、〇〇に困ることはありませんか?」
- I(Implication)示唆質問:「その課題が続くと、患者さんへの影響はどうなりそうですか?」
- N(Need-payoff)解決質問:「もし〇〇が改善されれば、どういったメリットがありますか?」
このように、質問を重ねることで、医師自身が“語りたくなる”空気をつくることができます。そして、語られた内容の中にこそ、MR・MSLが提供すべき情報の核心があるのです。
最近では、このSPIN話法よりも現場に応用しやすいより実践的な方法も提唱されています。
一方通行の説明で失注したケース
ある領域で新薬を担当した若手MRは、医師に対して「エビデンスの強さ」を一方的に説明し続けた結果、面談の途中で話を打ち切られてしまいました。
後日、その医師が別の企業のMSLと長時間ディスカッションしていたことがわかり、落胆したそうです。
何が違ったのか?
それは、「相手の関心」に迫ったかどうかの違いです。前者は自分の伝えたいことを話し、後者は医師の語りたいことを引き出したのです。
医師との対話における“スキル優先順位”
これまでに必要とされていたMRとしてのスキルの優先順位と現在必要とされているスキルの優先順位はつぎのように変化しています。
【従来のスキル優先順位】
1. 製品知識
2. 説明力
3. 論理的展開力
⇓ 環境変化によりシフト
【現在のスキル優先順位】
1. 質問力(相手を理解する力)
2. 傾聴・共感力(信頼構築の鍵)
3. 製品知識(適切なタイミングで提供)
このように、「伝える力」から「引き出す力」へのシフトが求められています。
変化を恐れず、対話力を磨こう
MR・MSLという仕事は、単なる情報提供者ではなく、「対話によって価値を共創する存在」へと進化しています。
そのためには、商品説明のトークスクリプトを覚えるよりも、「相手の言葉に耳を傾け、問いかける技術」を身につけることが何より重要です。
このブログが、読者の皆さんにとって「自分の対話のあり方」を見直すきっかけとなり、医師との関係性を再構築するヒントになれば幸いです。
今後も、製薬業界における「質問型コミュニケーション」や「交渉スキル」の実践知をご紹介していきますので、ぜひご自身の現場でも試してみてください。
プロフィール
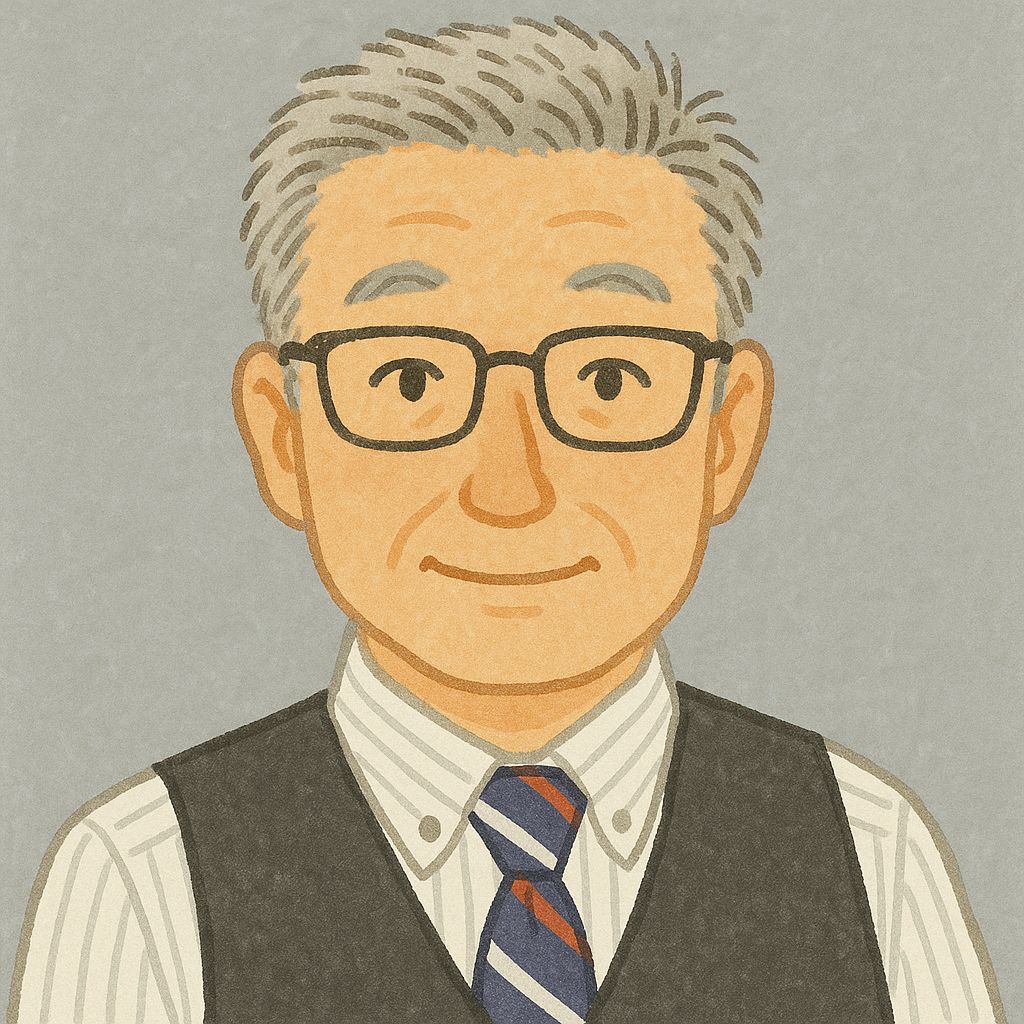
杉浦敏夫(すぎうら・としお)
1965年、長野市生まれ。名古屋大学工学部合成化学科卒業後、国内の製薬会社に入社。
プロダクトマネージャーとして大型新薬の上市を手がけた後、学術部、プロダクトマーケティング部、臨床開発部、教育研修部の部長職、営業部門では東京支店長などを歴任する。
日本人を対象としたエビデンス構築の必要性に着目し、多くの臨床試験の企画・運営を主導。そのうち代表的な2つの研究の結果は、国際的に権威のある医学専門誌に掲載され、国内の診療ガイドラインにも引用されている。
数多くのトップ・オピニオン・リーダーとの対話を通じて「質問の力」の本質に触れ、営業力強化の分野で著名な「質問型営業®」開発者・青木毅氏に師事。
現在は、第一線で活躍する営業職やマネージャーを支援する取り組みに注力している。趣味はカメラ、ソフトボール、ゴルフ、温泉旅行。
人気PodCast番組『青木毅の質問型営業』に著者として出演(第540回, 2025年9月19日配信)。
