【説明しない勇気 5】「また遮られた…」を卒業する。医師の信頼を勝ち取る「質問から始める」面会術
会話がうまく噛み合わないのは「入り方」に原因がある
「先生、今日も少しだけお時間よろしいでしょうか?」
そう声をかけて説明を始めた瞬間に、医師の反応が薄かったり、話の途中で「いや、それは…」と遮られてしまったり。MRやMSLのみなさんであれば、こうした経験に心当たりのある方は多いのではないでしょうか。
私自身、若いころは、この“入り方の壁”に何度も悩まされました。どれだけ準備をしても、最初の会話がスムーズにいかないと、その面会全体が空回りしてしまう。特に忙しい診療の合間では、こちらの話を最後まで聞いてもらえること自体が稀でした。
では、どうすれば医師との会話がスムーズに始まり、拒絶や反論を回避しながら信頼を積み重ねていけるのか? その答えは、「説明」ではなく「質問」から始めるというシンプルかつ強力な発想の転換にあります。
面会の主導権は「伝える」側ではなく「引き出す」側にある
多くの製薬パーソンが、面会前に「今日はこの製品のポイントをどう説明しようか」と考えて準備します。ですが、この構え方がかえって“売り込み”の印象を強め、医師との距離を生んでしまうことがあります。
そこで私は、こう切り替えるようにお勧めしています。
「今日はこの先生から、どんな考えを引き出したいか?」
「何を“聞くか”をあらかじめ準備する」
このマインドセットが変わると、面会の空気がまるで変わります。
たとえば、質問項目を事前に4〜5個ほど用意してメモしておくと良いでしょう。
このような問いかけがきっかけとなり、医師の考え方や価値観が見えてきます。それに対して、こちらが持っている情報や資料を“回答”として提供することができれば、情報が一方通行ではなく「対話のキャッチボール」になります。
「質問型」のコミュニケーションは医師の思考の地図を描く技術
質問型のアプローチの魅力は、相手の“思考の土台”に触れられることにあります。
たとえば、ある施設の医師にこんな質問を投げかけたことがありました。
「○○の患者さんに対して、診療方針ってここ数年で変化はありますか?」
すると、その先生は現場で感じている医療課題、地域特性、院内の診療体制など、多くの背景情報を語ってくれました。
結果として、面会は単なる情報伝達ではなく、“共に考える時間”へと変わっていきました。
このように、質問を起点にすることで「自律的な対話」が生まれます。医師自身が話すことで、自分の思考を整理し、その延長線上で私たちの情報に“意味づけ”をしてくれるのです。これは、こちらが一方的に説明するだけでは絶対に得られないディテーリングの成果と言えるでしょう。
質問とは「敬意」と「共創」の最初の一歩
質問という行為には、大きく2つのメッセージが込められています。
ひとつは、「相手の考えを尊重しています」という敬意。
もうひとつは、「一緒に対話をつくりたい」という共創の姿勢です。
医師の立場に立ってみれば、一方的に説明されるよりも、「先生はどうお考えですか?」と尋ねられた方が、はるかに気持ちよく話せるはずです。そして、会話の“主導権”は質問する側にあり、質問には話題の方向性をコントロールする力があるのです。
つまり、いかに的確に質問をできるかが交渉術の第一歩であり、もっとも信頼を築けるトークスキルなのです。
次回の面会では、ぜひ、説明のしかたではなく、質問のしかたの工夫に注力してみて下さい。それが、信頼ある情報提供活動への確かな一歩になります。
プロフィール
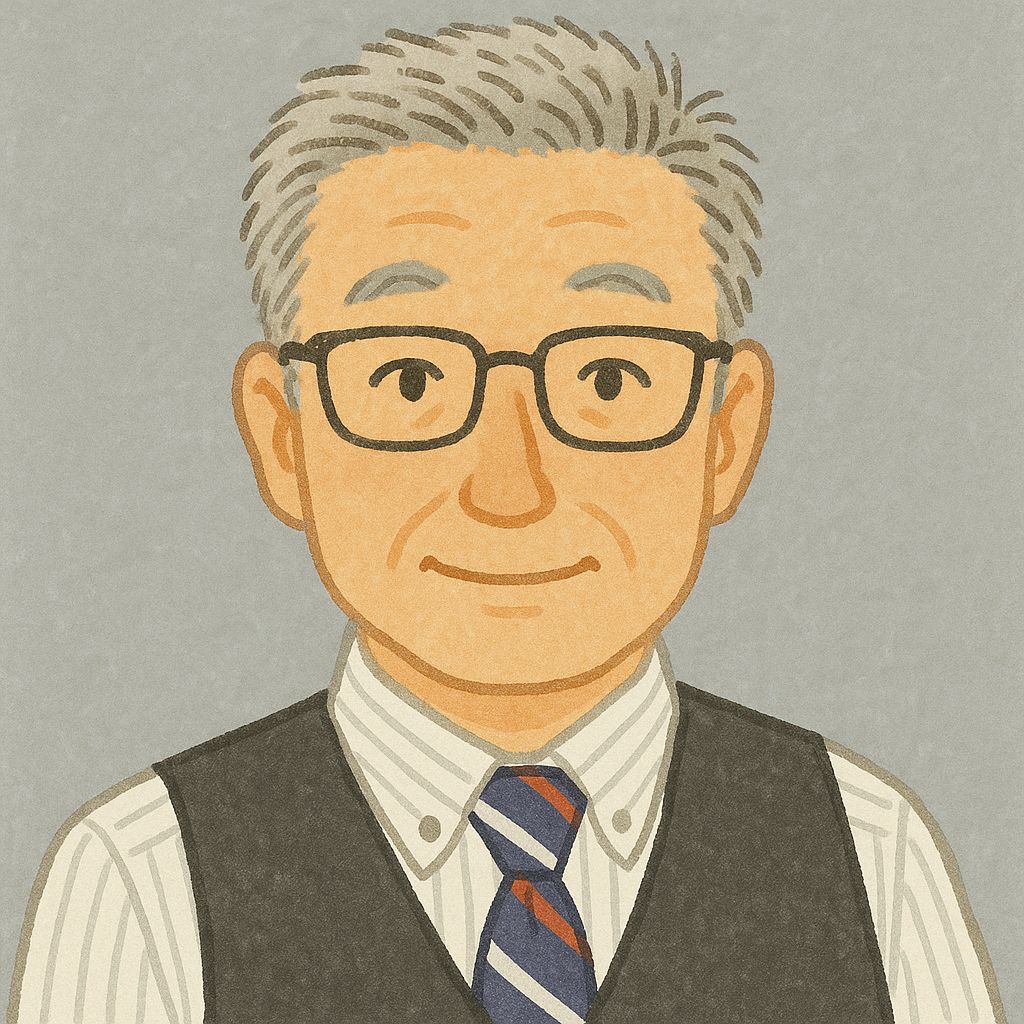
杉浦敏夫(すぎうら・としお)
1965年、長野市生まれ。名古屋大学工学部合成化学科卒業後、国内の製薬会社に入社。
プロダクトマネージャーとして大型新薬の上市を手がけた後、学術部、プロダクトマーケティング部、臨床開発部、教育研修部の部長職、営業部門では東京支店長などを歴任する。
日本人を対象としたエビデンス構築の必要性に着目し、多くの臨床試験の企画・運営を主導。そのうち代表的な2つの研究の結果は、国際的に権威のある医学専門誌に掲載され、国内の診療ガイドラインにも引用されている。
数多くのトップ・オピニオン・リーダーとの対話を通じて「質問の力」の本質に触れ、営業力強化の分野で著名な「質問型営業®」開発者・青木毅氏に師事。
現在は、第一線で活躍する営業職やマネージャーを支援する取り組みに注力している。趣味はカメラ、ソフトボール、ゴルフ、温泉旅行。
人気PodCast番組『青木毅の質問型営業』に著者として出演(第540回, 2025年9月19日配信)。
