【説明しない勇気 7】MSLの真価は「売り込まない」ことにある。プロモーションの枠を超えた“知の橋渡し”の技術
「営業しないMR !?」 MSLへの誤解と現場のすれ違い
「MSL(Medical Science Liaison)って、営業しないMRみたいなものでしょ?」「学術的な説明をしてくれる専門MRみたいな感じですよね」
これは、製薬企業内の他部門や時には医師サイドからも聞こえてくる“なんとなくのイメージ”です。私自身、現場を同行する中で、こうした誤解が根強く存在することを何度も感じてきました。
MSLのみなさんは日々、科学的な見地から医療関係者と向き合い、専門的な情報交換を続けています。しかし、まるで営業と同じ「数字を持った活動」と見なされ、組織内の評価指標もあいまいなまま、誤解された役割を期待される――そんな構造的なズレが現場を悩ませています。
今回はこの「MSLの本質とは何か?」について、改めて立ち止まり、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
MSLの真価は“非プロモーション領域”にある
まず確認しておきたいのは、MSLの活動は販売情報提供活動には該当しない、いわば「非プロモーション領域」であるという点です。
具体的な活動内容は以下のようなものです:
- 治験中または未承認薬に関する医学的・科学的情報の提供
- アンメット・メディカルニーズの探索とフィードバック
- アドバイザリーボードの設計・実施とファシリテーション
- 医師の論文化や自主研究の支援
- 診療ガイドラインや医学会情報の共有
こうした業務は、いずれも「売上」を直接目的とするものではないのがポイントです。
ここで重要なのは、「売る意思がないからこそ話ができる」という信頼の前提が、MSLという職種の本質を支えているということです。医師は極めて情報リテラシーの高い存在であり、意図が見え透いた情報提供には非常に敏感です。だからこそ、MSLの“中立的な立場”が持つ意義は大きいのです。
しかし、そのMSLが「営業部門の延長線上」に見えてしまった瞬間、その活動はステルスマーケティングと誤解されるリスクをはらみます。たった一つの言葉尻や、場の設計ミスが、企業としての信頼を揺るがすことすらあるのです。
なぜ誤解されるのか? 交差する現場の論理
では、なぜMSLという職種に誤解が生まれてしまうのでしょうか?
理由の一つは、「社内での棲み分けの曖昧さ」です。営業部門との連携を強めることで、訪問目的や情報提供の線引きが不透明になると、現場では混同が起こりやすくなります。
MSLの活動は営業的であってはならない…というのが業界ルールの前提ですが、営業部門と一切関わってはいけない!というようなコンプライアンスの過度な遵守は、両部門の軋轢を生み組織に不穏な影を落としてしまう懸念も考えられます。本来、社会に貢献することを目指す企業としては、MSLやメディカル部門と営業部門とは、密に連携することが必要であり重要です。
一方で、MSLの活動の中にわずかでも“営業色”が混入すると、医師の表情は一気に曇り「ああ、結局プロモーションか」と感じさせてしまうのです。
MSLに対する誤解のもう一つの要因は、MSL自身が“説明役”に寄りすぎてしまうことです。専門知識に長けているがゆえに、「伝える」「教える」姿勢が強くなりすぎると、対話の場が“学術講義”に傾いてしまいます。
MSLに必要なのは、「知識を見せること」ではなく、「知識を橋渡しすること」です。相手の関心やニーズを“聞き取る力”、そして共に議論を紡ぎ出す“対話の設計力”こそが求められます。
MSLが輝くための関係性デザインとは
では、どうすればMSL本来の価値を正しく認識してもらえるのでしょうか?
私が現場で意識しているのは、「接点設計」の初期段階から“非営業性”を強く明示することです。たとえばアポ取りの時点で「今回の目的は純粋に研究動向の確認と、先生のご専門領域に関するご意見を伺うためです」と明言する。
また、対話の構成も「質問」からスタートし、「一方的な説明」はあくまで補助的にとどめる。これはMRにも共通しますが、質問型のコミュニケーションは「情報の出し手」ではなく「共に考えるパートナー」という立場を築くうえで非常に有効です。
MSLは、医師と製薬企業の“知の橋渡し役”です。営業とは違う地点に立ちながら、しかし製品価値の土台を支える存在――それがMSL本来の姿だと私は思っています。
その真価が発揮されるのは、「売らないこと」を貫いたときなのです。
MSLという職能に、もう一度誇りを持つために
MSLという職種は、まだ業界全体での理解が発展途上にあると感じます。誤解され、営業的な要素と混同されることも多いですが、それだけに“本来の在り方”を体現できるかどうかが、企業の信頼に直結する時代です。
もし、今みなさん自身が「営業寄りの期待をされている気がする」「説明要員と見られているかもしれない」と感じているなら、ぜひ一度、自らの立ち位置と活動目的を見直してみてください。そして、医師という最難関のプロフェッショナルと対等に渡り合えるコミュニケーション能力をぜひ身に着けて頂きたいと思います。
MSLという役割は、製薬業界における“透明な知の流通”を支える極めて重要な存在です。そして、それを正しく機能させる鍵は、“説明”よりも“関係性の設計”を可能にする交渉力にあるのです。
「営業ではない」からこそ語れる対話を、あなたの手で築いていってください。
プロフィール
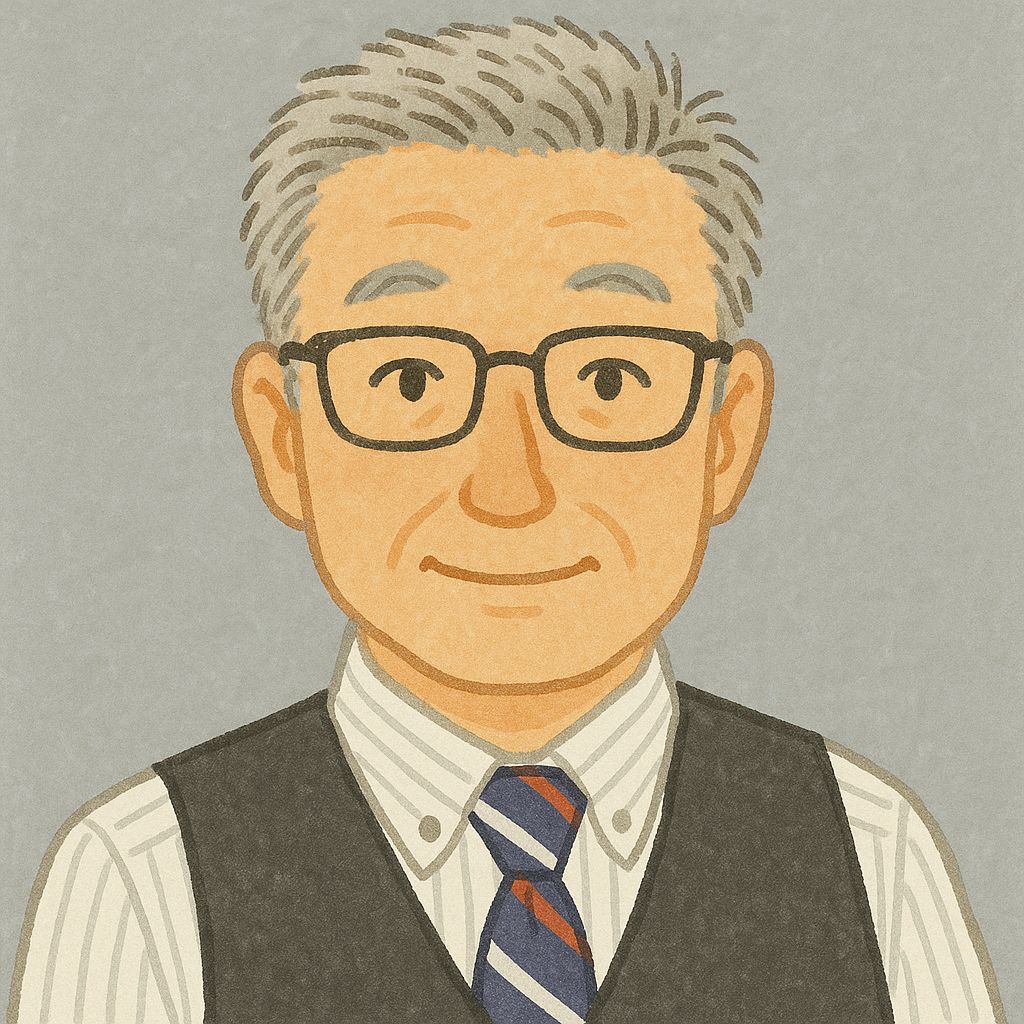
杉浦敏夫(すぎうら・としお)
1965年、長野市生まれ。名古屋大学工学部合成化学科卒業後、国内の製薬会社に入社。
プロダクトマネージャーとして大型新薬の上市を手がけた後、学術部、プロダクトマーケティング部、臨床開発部、教育研修部の部長職、営業部門では東京支店長などを歴任する。
日本人を対象としたエビデンス構築の必要性に着目し、多くの臨床試験の企画・運営を主導。そのうち代表的な2つの研究の結果は、国際的に権威のある医学専門誌に掲載され、国内の診療ガイドラインにも引用されている。
数多くのトップ・オピニオン・リーダーとの対話を通じて「質問の力」の本質に触れ、営業力強化の分野で著名な「質問型営業®」開発者・青木毅氏に師事。
現在は、第一線で活躍する営業職やマネージャーを支援する取り組みに注力している。趣味はカメラ、ソフトボール、ゴルフ、温泉旅行。
人気PodCast番組『青木毅の質問型営業』に著者として出演(第540回, 2025年9月19日配信)。
