【説明しない勇気 8】MRとMSLの「境界」が最強の武器になる――製薬ビジネスの競争力を高める“分業と連携”の極意
「営業してはいけない人」がなぜ必要なのか?
「MSLって、何をしているのか、正直よくわからない」
製薬会社の営業の管理職や現場の方と話していると、いまだにこうした声を耳にすることがあります。実際、私も一般の方からMSLの活動について問われたとき、明確に説明できないケースが多々ありました。
一方で、大学教授クラスの医師との面会に立ち会ったとき、MSLの一言が現場の空気を一変させ、製品の評価や関心を大きく高めた場面にも幾度となく立ち会ってきました。そこで私が強く実感したのは、「MSLは“営業していない”からこそ、信頼を得られる存在である」という事実です。
MSLを理解し、正しく活かすことは、今後の製薬ビジネスにおける競争力そのものにつながる――今回はそんなお話をお届けします。
MSLとは“売らずに売る”を体現する交渉のプロである
MSL(Medical Science Liaison)の本質的な役割は、営業ではありません。自社製品を推すことでもなければ、処方促進のためのプレゼンをすることでもありません。彼らの使命は「医学的知見のギャップを埋めること」。つまり、医療現場が抱える課題と、自社が持つ科学的リソースとの“橋渡し”を行うことにあります。
現場での活動を整理すると、MSLにできることとしてはいけないことは明確に分かれます。
MSLにできること:
- 医学的中立性を保った学術的対話
- 論文やエビデンスの解釈に関する建設的な議論
- KOL(キーオピニオンリーダー)との共同研究の構想提示
- 医師のニーズや気づきを社内にフィードバック
MSLがしてはいけないこと:
- 製品の優位性を積極的にアピールすること
- 未承認薬・適応外の有効性に言及すること
- 接触頻度を稼ぐこと自体を目的とした訪問
- 営業部門と一体化して“ダブルディテール”のような形をとること
これらの境界を曖昧にしてしまえば、MSL個人への信頼はもちろん、制度そのものの信頼性が損なわれてしまいます。
営業とMSLは「分けて、つなげる」のが最強の戦略
私はこれまで、MRとMSLがうまく連携していた現場と、そうでなかった現場の両方を数多く見てきました。前者では、医師との会話が「深まり」、後者では「途切れ」ます。この違いを生むのは、役割分担と相互尊重の文化です。
たとえば、あるMSLが学会で得た最新知見を社内に共有し、その情報をもとにMRが面談準備を行った結果、医師から「そこまで勉強しているなら」と高い評価を得たことがありました。また、MSLが医師から受け取った臨床現場の“違和感”をプロジェクトチームにフィードバックし、新たな製品コンセプトが生まれた事例もあります。
ここで重要なのは、MSLが営業色を出さずに“対話の土壌”を整え、MRがその場を活かして“ビジネスの種”を育てるという構造です。どちらか一方では成り立ちません。
MSLは「売らずに売る」ことを可能にする、いわば製薬企業における戦略的交渉術の使い手。この視点に立てるかどうかで、組織全体のパフォーマンスが大きく変わるのです。
MSLを“高学歴ディテーラー”にしないために
残念ながら一部の企業では、MSLの存在がまだ「高学歴なディテーラー」扱いされている現状があるのではないでしょうか。これは、非常にもったいないことです。MSLの価値を最大化するためには、組織としての認識転換と制度設計が不可欠です。
- MSLには営業目標を課さない
- 成果指標に“面談数”や“資料提示数”を用いない
- 評価に「医師からの信頼」「社内へのインサイト還元」を含める
- 営業部門と情報連携はするが、決して“混在”はさせない
こうした取り組みによって、MSLは単なるプレゼン要員ではなく、医師と製薬企業の架け橋としてその真価を発揮することができます。
MSLの言葉が医師に届くのは、営業ではないからこそ。中立性・科学性・信頼性という3つの“武器”を最大限に活かす環境づくりこそが、これからの製薬企業に求められる視点です。
「売らない」からこそ信頼され、「売れていく」組織へ
医師が本当に心を開くのは、「この人は売り込みではない」と確信したときです。そして、その確信を最も自然に生み出せるのが、MSLのような非営業職なのです。
とはいえ、MSLがどれだけ優れた活動をしていても、社内の理解がなければ活かしきれません。MRやMA、マーケティング部門の一人ひとりが、MSLの立場と役割を正しく理解し、共に動く文化をつくっていくことが求められています。
MSLは「売らずに売る」という不思議な力を持つ存在です。だからこそ、その力を戦略的に活かすために、私たちは今一度「MSLとは何か?」を問い直す必要があるのではないでしょうか。
プロフィール
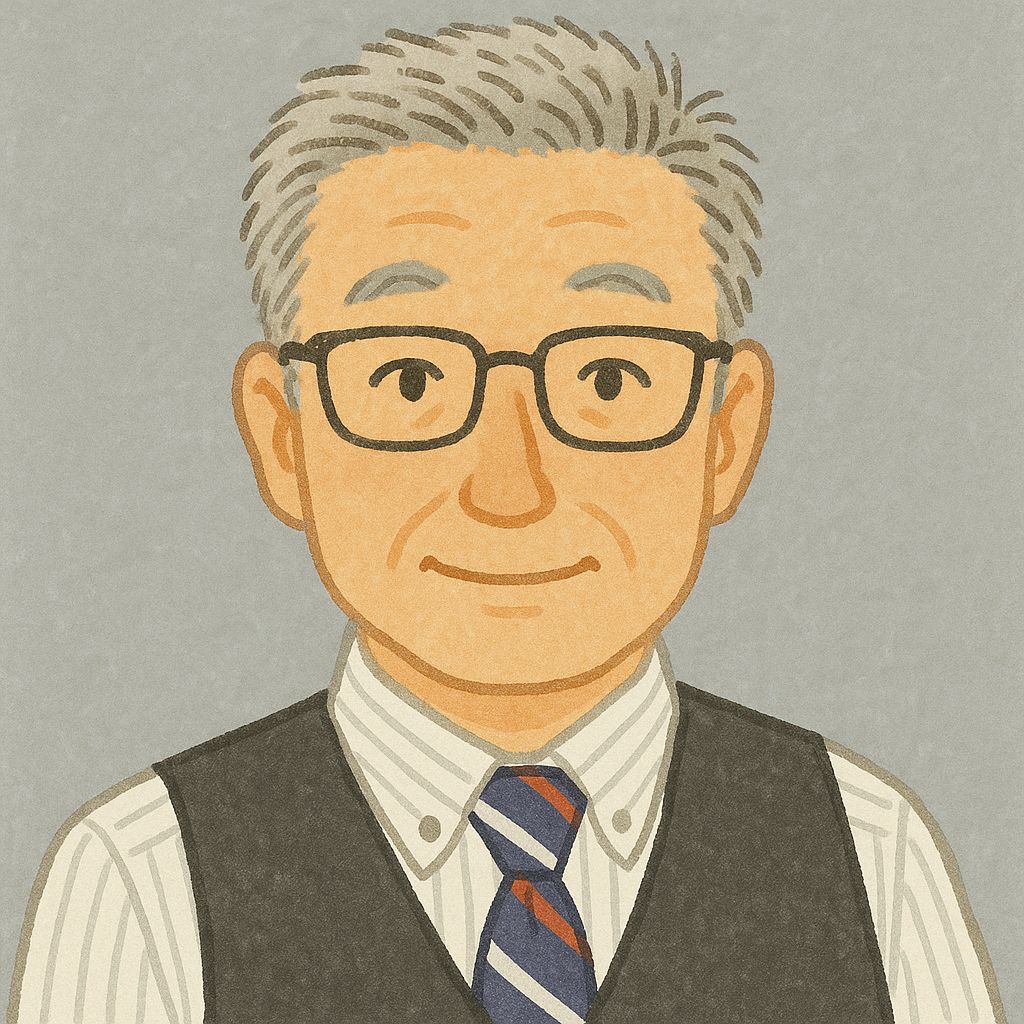
杉浦敏夫(すぎうら・としお)
1965年、長野市生まれ。名古屋大学工学部合成化学科卒業後、国内の製薬会社に入社。
プロダクトマネージャーとして大型新薬の上市を手がけた後、学術部、プロダクトマーケティング部、臨床開発部、教育研修部の部長職、営業部門では東京支店長などを歴任する。
日本人を対象としたエビデンス構築の必要性に着目し、多くの臨床試験の企画・運営を主導。そのうち代表的な2つの研究の結果は、国際的に権威のある医学専門誌に掲載され、国内の診療ガイドラインにも引用されている。
数多くのトップ・オピニオン・リーダーとの対話を通じて「質問の力」の本質に触れ、営業力強化の分野で著名な「質問型営業®」開発者・青木毅氏に師事。
現在は、第一線で活躍する営業職やマネージャーを支援する取り組みに注力している。趣味はカメラ、ソフトボール、ゴルフ、温泉旅行。
人気PodCast番組『青木毅の質問型営業』に著者として出演(第540回, 2025年9月19日配信)。
