【説明しない勇気 4】説明するほど医師が冷たくなるのはなぜ?MR・MSLが陥る『説明の罠』と脱出の鍵
なぜ説明すればするほど、医師の反応が冷たくなるのか?
「ちゃんと説明したのに、まったく響いていない気がする……」
これは現場で頑張るMR・MSLの方から何度も聞いたフレーズです。エビデンスを揃え、丁寧に製品特性を話したはずなのに、医師の反応は素っ気ない。むしろ反論されたり、不信感すらにじませてきたりする――そんな経験、ありませんか?
私自身、現場で何度もこの“壁”にぶつかりました。当時は、「説明の仕方が悪かったのか?」「もっと情報量を増やすべきだったか?」と自分を責めました。でも、違ったのです。問題は「説明する」ことそのものにあったのです。
「説明」より「納得」――医師が動くのはどんなときか
医師という職業は、他の業種と比べても圧倒的に論理的です。日々、患者の病態と向き合い、診断と治療方針を明確に組み立てていく中で、「情報をどう判断するか」というスキルは磨きに磨かれています。
そんな医師に対し、私たち製薬パーソンがいくら丁寧に説明しても、受け取る側の頭の中ではこういう思考が働いています。
- 「これはもう知っている情報だ」
- 「そのデータにはこんなバイアスがあるのでは?」
- 「なぜ今、これを自分に言ってくるのか?」
つまり、こちらがどれだけ一生懸命に話しても、それが医師にとって「自分の判断を揺るがすような“納得感”」に結びついていなければ、ただの“説明の押し付け”として処理されてしまうのです。
さらに、説明の中に“説得の意図”が感じられると、それは警戒感につながります。「売り込みか?」という視線が走ると、以後の面談は一気にハードモードに。これはMR・MSL側の努力不足ではなく、アプローチの構造そのものに問題があると言えるでしょう。
「質問」と「共感」で医師の本音を引き出す
では、どうすれば医師の“納得”を引き出せるのか。その鍵は、「説明」ではなく「対話」、つまり質問を起点としたコミュニケーションにあります。
たとえば私が実践して効果を感じたのは、説明に入る前にこう問いかけることでした。
「先生のところの高齢の患者さんで、最近何か変わってきていることはありませんか?」
すると医師の口から、「いやね、最近うちの外来では〜」と話が始まります。その話に耳を傾け共感しながら、関連するエビデンスや薬剤の注意点などに自然とつなげていく。すると「このMRは話を聞いてくれている」という信頼感が生まれ、説明内容にも耳を傾けてもらえるようになるのです。
このような質問と共感のアプローチは、医師の関心領域を確認しながら話題を選べるため、説明が“押し付け”にならず、相手のニーズと自然に接続できます。
心理学的にも、人は自分で発見した情報に対してのほうが記憶に残りやすく、受け入れやすいという傾向があります。質問によって医師自身が答えを導き出せば、それは“納得”に変わるのです。
「説明しない勇気」が、信頼関係を築く第一歩
MR・MSLとして「情報提供をしなければならない」「伝えなければならない」という使命感は当然のことです。でも、その気持ちが強くなりすぎると、説明が“独り相撲”になってしまう危険があります。
特に新しい製品や自信のあるデータを紹介したいときほど、そのリスクは高まります。けれど、その情報を受け取る医師にとっては、「今、知りたい」「今、必要だ」と感じられなければ響かないのです。
だからこそ、説明する前に質問を。
質問によって関心を探り、ニーズを明らかにし、その上で必要最小限の情報を添える――このスタイルが、医師との信頼を築く最も効果的な方法だと、私は現場で繰り返し実感してきました。
製薬業界における交渉術とは、「話す技術」ではなく「聞く技術」です。
もし、あなたが最近の面談で壁を感じているのなら、「説明を頑張る」方向ではなく、「質問を工夫する」方向にシフトしてみてください。
その一歩が、医師との対話を変え、あなたのプロフェッショナリズムをより高めてくれるはずです。
プロフィール
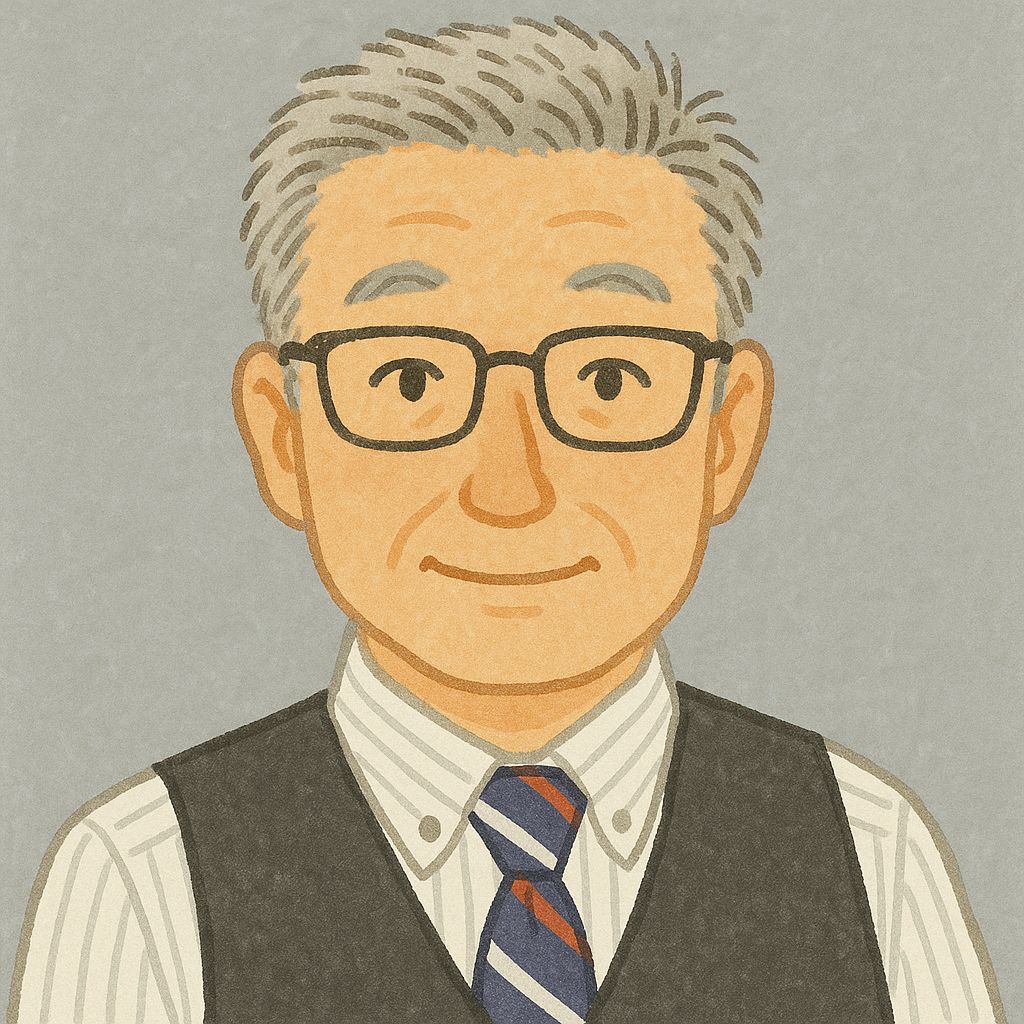
杉浦敏夫(すぎうら・としお)
1965年、長野市生まれ。名古屋大学工学部合成化学科卒業後、国内の製薬会社に入社。
プロダクトマネージャーとして大型新薬の上市を手がけた後、学術部、プロダクトマーケティング部、臨床開発部、教育研修部の部長職、営業部門では東京支店長などを歴任する。
日本人を対象としたエビデンス構築の必要性に着目し、多くの臨床試験の企画・運営を主導。そのうち代表的な2つの研究の結果は、国際的に権威のある医学専門誌に掲載され、国内の診療ガイドラインにも引用されている。
数多くのトップ・オピニオン・リーダーとの対話を通じて「質問の力」の本質に触れ、営業力強化の分野で著名な「質問型営業®」開発者・青木毅氏に師事。
現在は、第一線で活躍する営業職やマネージャーを支援する取り組みに注力している。趣味はカメラ、ソフトボール、ゴルフ、温泉旅行。
人気PodCast番組『青木毅の質問型営業』に著者として出演(第540回, 2025年9月19日配信)。
